【愛犬のホリスティックケア】胃腸編(嘔吐、軟便、下痢)
クイズです!「嘔吐と下痢だと体に負担なのはどちらでしょうか?」
今回は、この時期崩しやすい胃腸の手当てについて。
消化管はいろいろなものが入ってくるので影響が最も受けやすい器官でもあります。
今、受講中の「愛犬のお手当法」の胃腸編を学んだものをまとめてみました。
今日の内容
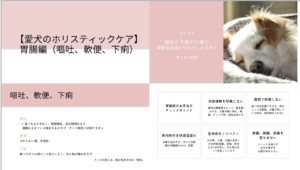
目次
嘔吐、軟便、下痢
- 嘔吐:食べたものを吐く。胃液嘔吐、消化物嘔吐など
健康からきている嘔吐もあるので、すべて病気とは限りません。
お腹がすきすぎて吐いてしまうこともあります。
- 軟便:やわらかい便。水溶性。
- 下痢:食べてすぐに便として出てしまう。水と熱が奪われます。
冒頭のクイズの答えは、体に負担なのは「嘔吐」
心と体の健康を保つ秘訣
腸は24時間自動に動いています。
そのためには、水が必要になります。
水がないだけで下痢や嘔吐になります。
水をたくさん飲むと下痢をしてしまいそうですが、そんなことはないそうです。
心も大事
メンタルによる心因性の嘔吐や下痢、軟便もあります。
ストレスを溜めないようにすることも大切です。

胃腸病のお手当のチェックポイント
① 自律運動を邪魔しない
② 異物で刺激しない
③ 体内体外を快適温度に
④ 生命体をリスペクト
⑤ 肝臓、膵臓、胆嚢を怒らせない
①~⑤をチェックして、満たさないところを満たしてあげる。
① 自律運動を邪魔しない
普段は繊維質をとって、腸を動かせる。
お腹が緩い時は、繊維、タンパク質、脂質は減らします。
歩かせて大丈夫なようなら歩かせる。
歩かない、歩けない犬はバランスクッションで平衡感覚刺激する。
② 異物で刺激しない
食べ物は栄養ですけど、体にとっては異物。
お腹が弱っている時は、固形物を入れない。
下痢・軟便時、ご飯をやめる人がいます。
絶食はあまりしない方がいい
お腹が空っぽになるので下痢や軟便は止まるけど
食べないことによって胃の調子が悪くなる
動いている組織なので、動きが悪くなります。
動かしながら直すのがベスト!
原因を解決せずに薬物療法してその場しのぎになってしまいます。
③ 体内体外を快適温度に
お腹を温めすぎ、冷えに注意してください。
犬は、腸が地面側のため、影響されやすいです。
冷やさないように
腹巻や低温カイロ、など
あずきの力やヘソ温灸、シルクの腹巻がおすすめ
温めすぎも注意
温めすぎると腸が動かなくなる。
通常は、排尿・排泄で体温を維持している。
気象に影響されやすいので室温や湿度(40~60%)
台風や秋雨前線などの変化も急変を呼ぶので気をつけてください。
④ 生命体をリスペクト
犬の胃、小腸、大腸には多くの生命体(細菌、真菌、原虫など) が生活し、犬と助け合って共生しています。
発酵物(ビオフェルミン、ヤクルト、ミルミル、納豆、梅干し)を与えて整腸。
赤い肉や脂は、悪い生命体が増える傾向があります。
⑤ 肝臓、膵臓、胆嚢を怒らせない
- ストレスを減らす
- 水分を増やす
- お腹を冷やさない
肝臓、膵臓、胆嚢
膵臓:消化酵素を出しているところ。直近の元気をコントロール
食べ物とメンタルに敏感
肝臓:デトックス、オシッコの源生成、元気を貯めるなどなど
いつもハードワークで寡黙だがイライラしやすい
胆嚢:肝臓からいただく物質を貯めている。食べ物に反応して 腸に排出。
膵臓、肝臓、胆嚢はとても仲良し。
どこかが悪くなると全部悪くなります。
肝臓、膵臓、胆嚢はとても大切な臓器なので、検査をおすすめされていました。
まとめ
今日は、学んでいる講座の胃腸のお手当について書きました。
人と同じで消化管はとても大切な臓器。
人と一緒で最近の犬は食べ過ぎ傾向にあります。
胃腸を休めてあげることも大事で、
悪くなったからといって薬で抑えるよりも
根本的に胃腸のケアをしてあげることが大事です。
明日は、飼い主の頭をなめた猫が心不全について書きます。


Wow, marvelous blog format! How long have you ever been running a blog for?
you made running a blog look easy. The full glance of your web site is excellent, let alone the content!
You can see similar here sklep internetowy